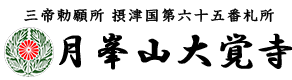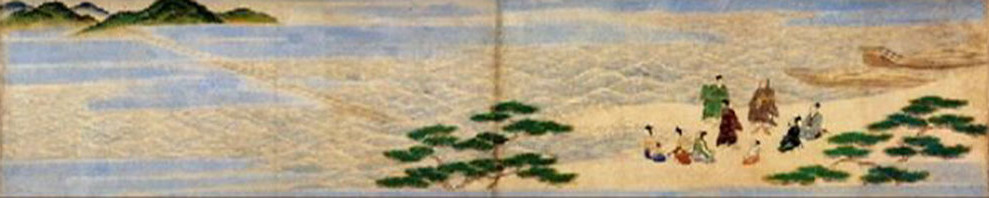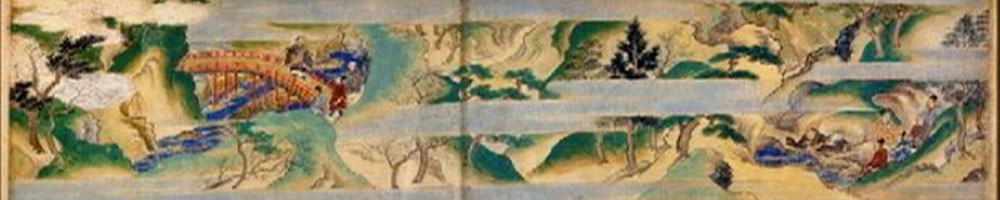弁天堂
大覚寺の弁才天と洛中・東北院の弁才天女
能楽「船弁慶」「芦刈」の舞台である尼崎大覚寺を開創した、東大寺戒壇院円照上人の弟子琳海上人は、後深草上皇の病悩に際して、門弟を率いて御所に参上し、千手陀羅尼による加持を行いました。
また、後伏見天皇の中宮(広義門院)の御産祈願の折には、七仏薬師による放生を修し、目出度く量仁親王(光厳天皇)生誕により「貴坊の効験」と大がかりな祝宴が開かれました。
大覚寺の弁才天は、(現在の弁天堂は弁天社唐門を鞘堂に改築したもので、社紋には西園寺家の左三つ巴の家紋が蛙股に刻まれています:市指定文化財)大覚寺市庭の市神様で、中学、高校で習う『覚一本・平家物語』を完成させた琵琶法師の巨匠・覚一検校以下の琵琶法師たちの守護神でもありました。
大覚寺開創の後、琳海上人が復興した能楽「東北」の舞台であり、御所の東北に位置した、洛中・東北院にも、妙音弁才天女が祀られ盛況であったようです。
また、経典に準拠した漢字表記では「弁才天」ですが、財宝神としての性格が付与されて、「弁財天」と表記する場合も多いようです。
西園寺家と妙音弁才天女
西園寺家は、藤原氏の流れを汲む公家で、鎌倉時代(約700年前)公経が京都(北山荘)の別邸に建立した寺の名前で、現在の鹿苑寺(金閣寺)にある舎利殿(金閣)は、足利義満が西園寺家よりこの土地を譲られて建てたものです。
西園寺家では、琵琶を奏でる弁才天を守り神とし、屋敷内の“妙音堂”に妙音弁才天が祀られていました。現在、この妙音堂は「白雲神社」と名前を変えて、京都御苑の中の西園寺家の屋敷跡(立命館発祥の地)に残っています。
本尊である画像は、西園寺寧子(広義門院)から、その実子の光厳天皇、孫の崇光天皇を経て、伏見宮家に代々伝えられました。伏見宮家の琵琶は西園寺家の教えを受けたもので、伏見宮家の屋敷跡に建てられた京都出町の妙音弁財天のご本尊として現在祀られています。
覚一検校と平家物語
琵琶法師・覚一検校(かくいちけんぎょう)
『平家物語を読む会』
□指 導: 相愛大学教授
砂川 博 先生
□定例日: 毎月1回
(第3土曜日・午後2時から)
□場 所: 尼崎市立中央図書館
セミナー室
□主 催: 覚一検校顕彰会
※ 全巻講義が終わりましたので募集を終了致しました。
閻魔十王堂「返之堂(かえすのどう)」
大覚寺境内にはかつて「返之堂」と呼ばれた伝説に秘められたお堂がありましたが、明治十年の火災により焼失してしまいました。
この御堂は、江戸時代の『摂陽群談』『摂津名所絵図』などの文書にも登場する有名なお堂で、寺伝によりますと、一人の琵琶法師が「検校」(盲目の僧の最上位の官名)の資格を得るために京都に上る途中、鳴尾の沖で海賊に大金を奪われて殺されます。その後、海賊夫婦はその大金を元手に裕福な身になりますが、子供が海にさらわれてしまいます、ある夜、くだんの琵琶法師が夢枕に立ち、大切な自分の命とお金を奪った代わりに、子供をもらっていくと鳴尾沖の恨みを語ります。驚いた海賊夫婦は琵琶法師の供養のため、中世琵琶法師の活動の拠点のひとつであった大覚寺に、閻魔十王を安置した「十王堂」を施入しました。業悪善事をもって報いることから俗に「返之堂」と呼ばれました。
現在大覚寺には南北朝時代琵琶法師の巨匠・覚一検校が定めた『覚一本平家物語』が誰に伝えられたかを記した文書『覚一本平語相伝次第』(兵庫県重要文化財)が伝えられています。中世都市尼崎の母体となった大覚寺市庭は、彼ら琵琶法師の活動の拠点でもあり、その市神様である弁財天は琵琶法師の守護神でもありました。
復元した大覚寺の十王像の配置の特徴は、阪神淡路大震災の復興工事のための車両進入のために伐採した、立ち枯れになっていた楠木を材にして、大仏師・松本明慶師の手に依り、前述の伝説に基づき非業の死を遂げた琵琶法師が本地仏によって、浄土の世界へと昇天して行く様子が表現されています。
またインドの説話では弁才天は閻魔大王の長姉でもあり興味深いです。
( )の本地仏とは、
この姿が本来の姿で、十王に姿を変えてそれぞれの役目を果たされる。

二七日
初江(しょこう)王(おう)(釈迦如来)
偸盗(盗み)について取り調べる。
悪竜の棲む「三途の川」を渡った対岸に、懸(けん)衣(ね)翁(おう)と奪(だつ)衣(え)婆(ば)のニ鬼が衣服をはぎ取り衣領樹(えりょうじゅ)の枝に掛け罪の軽重を計る。

五七日
閻魔(えんま)王(おう)(地蔵菩薩)
閻魔庁には光明王院と善名称院のニ院があり、閻魔王は光明王院にある時、淨頗(じょうは)梨(り)の鏡に亡者の前生の善業悪業を映し出し、善名称院にある時は、地獄の救済者である地蔵菩薩として亡者を救い改心を促す。
六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天)の行き先を定める。