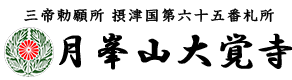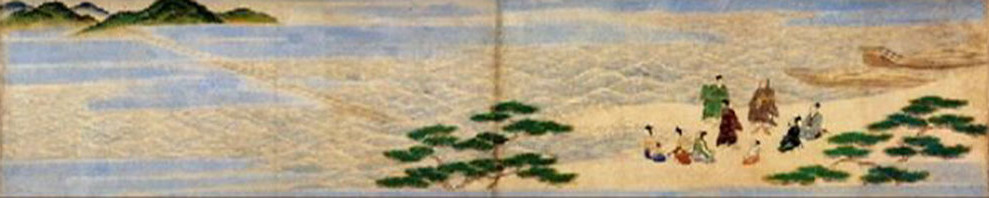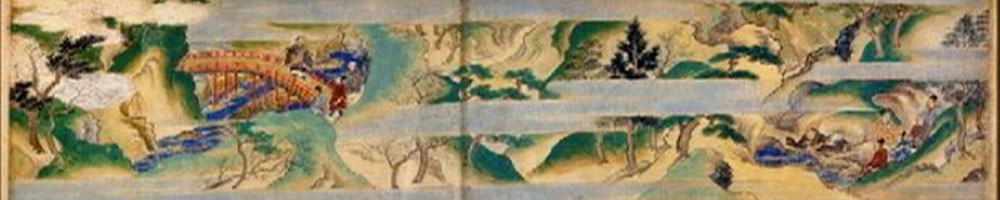聖天堂
尼崎藩御祈祷所と聖天堂
新城築城により、大覚寺は現在の寺町に移り「尼崎藩御祈祷所」を命ぜられ、藩主・藩領などの安寧豊楽(ぶらく)を祈願しました。
保存する版木に「大覚寺城、藩領百十九ヵ村(川辺郡・武庫郡・兎原郡・矢部郡)、五穀豊穣札」などの裏書が残ります。
当山に奉斎する歓喜天(聖天)は高野山・道範僧正ながく護持供養し、その後、慈洞上人に付属し、それより慈剛上人伝承し、当山天肇上人に譲られ、爾来歴代山主慇懃に護持致します。
寺録によれば、城主青山公より南蛮造りの殿堂の寄進を受け、文久3年(1863)には油屋喜兵衛の発願によって、万人浴油講が結成されたとあります。
現在の建物は青山公の南蛮造りを念頭に於き、昭和27年渋谷五郎氏設計によります。
参考:
__ 渋谷五郎・長尾勝馬共著「日本建築上・下」学芸出版
徳川幕府老中・青山幸成公と青山幸利公
青山大蔵少輔幸成(あおやまおおくらのしょうよしなり)公
江戸時代初頭、元和三年(1617)大阪城の西の守りとして、築城の名手として名高い尼崎藩2代目の城主・戸田采女正氏鉄(とだうねめのしょううじかね)公によって、開創以来の寺域に新城が築城され、当初大覚寺城と呼ばれました。
尼崎藩青山家初代の城主、青山大蔵少輔幸成公は徳川幕府老中として活躍され、江戸の青山家の下屋敷は江戸でも屈指の広大な敷地を幕府より与えられていました。東京青山の地名は、尼崎藩初代藩主青山幸成(よしなり)公の父、江戸奉行・関東総奉行を兼任し、老中として幕政において重きをなされた青山忠成(ただなり)公で、徳川家康公は鷹狩りに際し、見渡せる限りの土地を屋敷地に遣(つか)わすと言われて、この地域一帯を「青山」と呼ぶようになったそうです。「寛政重修諸家譜(かんせいちょうしゅうしょかふ)」によりますと「忠成すなわち馬をはせて巡視し、木に紙を結びて境界の標(しるし)とす。」とありますから、いかに重臣であったかが分かります。
さて、幸成公の戒名は「梅窓院殿前大府香譽淨薫大禪定門」と申されますが、仁徳天皇が「難波宮」に移された、尼崎の「難波の梅」が想起されます。また墓所は、高野山の奥の院の弘法大師の御廟の無明橋のすぐ近くに大きな五輪塔がありますが、東京青山にもご自身の戒名から名付けられた、広大な青山墓地を有する「梅窓院」にも在ります。東京青山は尼崎藩下屋敷があった場所で、青山侯の名前がその地名に残っています。
尼崎青山家の家紋は、「無地銭紋(裏銭紋)」の家紋と共に、大覚寺城に因み大覚寺の「葉菊紋(抱き菊の葉に菊)」をお使いになったと伝えています。
「葉菊紋」は天皇家より賜る紋で、十六葉菊花紋の天皇家を二枚の菊の葉で包みお守りする形であると言われています。近くでは明治天皇が西郷隆盛公に下賜されておられます。
青山大膳亮幸利(あおやまだいぜんのすけよしとし)公
尼崎城4代目の城主、尼崎青山家2代目の青山大膳亮幸利公は、寛永20年(1643)将軍徳川家綱より火事番を命ぜられ、消防をはじめ非常の際の警備の職につき、明暦三年に発生した江戸の大火(いわゆる明暦の大火)には手勢を引きつれ江戸城にかけつけ、上意を受けて各藩を督励し、消防や警備に当らせたことは有名です。その他にも大阪城の両度に亘る落雷炎上の際も、直ちに消防指揮の任につき更に天主閣の修復まで行なっておられます。
幸利公は『青大録(せいだいろく)』と呼ばれる逸話・嘉言善行の記録が残る名君でした。
貞享元年(1684)六十九才で尼崎に歿し、その遺言通り藩領の神戸大倉山に葬られました。それではなぜ藩領といえども、本拠地の尼崎城下から25キロも離れた神戸の大倉山に墓所を決められたのでしょうか。それは幸利公が尼崎藩主になられた時、楠木正成(まさしげ)公の戦没の地を̚比定され、顕彰する為に小さな五輪の石塔を建てられ、そして「松」と「梅」を植えられた場所であり、3代目幸督(よしまさ)公の時、「水戸黄門」で知られる水戸光圀(みとみつくに)公はその場所に「碑」を立てられ、いよいよ立派になったのが現在の「湊川神社」の起源だと言われています。2代目幸利(よしとし)公や3代目幸督(よしまさ)公が、ご自分たちが顕彰された楠木正成公に対し、同じ武将としての深い思いがあったから、その同じ場所をお二人の終焉の地に選ばれたのかもしれません。
この像は火事装束をした幸利公を古文書によって再現されたものです。
尚この当時の尼崎藩領は、神崎川以西から、「兵庫津」神戸の垂水までの、現在の西宮、芦屋、神戸の海岸線の村々に及び、五万石でありました。
また、尼崎藩青山家では歴代の城主の「幸」の字を「よし」と読み慣わします。