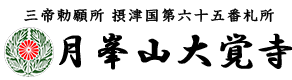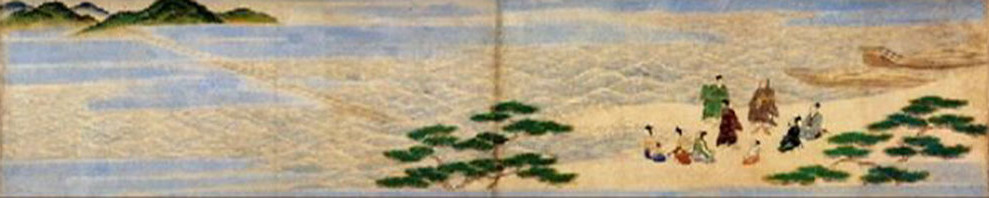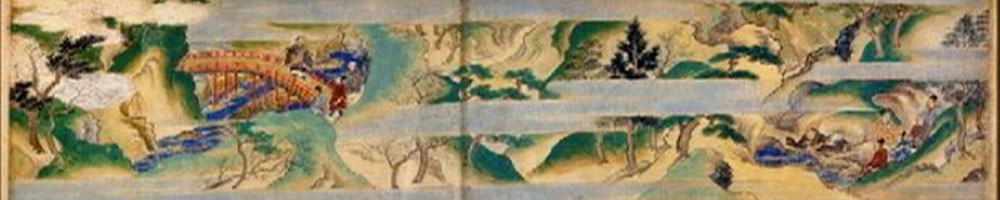琳海上人
大覚寺開創 琳海上人と葉菊紋
東大寺戒壇院 円照上人の弟子琳海上人、
大覚寺統・後宇多(ごうだ)天皇の御代、建治元年(1275)尼崎大覚寺を創建し、大覚寺長老となる、後に洛中・東北院を復興。
洛中・東北院は京都御所の東北に位置し、世阿弥の能楽「東北(とうぼく)」の舞台。
琳海上人略歴:
摂津の国に生まれる。
勝尾寺に入り、信覚と号す。
建長3年(1251)東大寺戒壇院に入る。
建長年間円照律師より受戒する。
正元元年(1259)大和戒光寺、淨因律師につき律蔵を聴講する。
正嘉元年(1257)石清水八幡宮、神宮寺、善法寺住持となる。
文永4年(1267)八幡宮宮司の菩提寺、八幡大乗院長老(座首)となる。
建治元年(1275)大覚寺長老となり、後に洛中・東北院を復興する。
摂津の国に生まれる。
勝尾寺に入り、信覚と号す。
建長3年(1251)東大寺戒壇院に入る。
建長年間円照律師より受戒する。
正元元年(1259)大和戒光寺、淨因律師につき律蔵を聴講する。
正嘉元年(1257)石清水八幡宮、神宮寺、善法寺住持となる。
文永4年(1267)八幡宮宮司の菩提寺、八幡大乗院長老(座首)となる。
建治元年(1275)大覚寺長老となり、後に洛中・東北院を復興する。
参考
__ 『円照上人行状記』 戒壇院凝然(ぎょうねん)著。
__ 『本朝高僧伝』 卍元師蛮(まんげんしばん)著
__ 『招提千歳伝記』 明律篇。唐招提寺蔵。

後深草天皇崩御
嘉元二年(1304)
7月1日東北院琳海上人千手観音陀羅尼を以て加持す。
廣義門院御産:(後伏見天皇の中宮)
延慶4年(1311)2月1日東北院琳海上人七仏薬師法修中毎旬放生あり。
放生に用いる魚介を尼崎及び天王寺今宮浦にて買う。
北朝第一代光厳天皇:
後伏見天皇(伏見天皇の第一皇子)の第一皇子。名を量仁(かずひと)親王。
母は前左大臣西園寺公衡(きんひら)の娘。寧子(ねいし)広義門院、
正和2年(1313)一条邸に生誕。
「時代背景」:
文永11年(1274)10月文永の役。元寇
建治元年(1275~1278迄)異国警護番役を定め防備の強化。
弘安4年(1281)7月 弘安の役。元軍、再度来襲。
文永11年(1274)10月文永の役。元寇
建治元年(1275~1278迄)異国警護番役を定め防備の強化。
弘安4年(1281)7月 弘安の役。元軍、再度来襲。
「記録文献」:
(管見記:かんけんき)
西園寺実兼(さねかね)の長男西園寺公衡(きんひら)の日記。
母は源道成の娘の源顕子(あきこ)。
(管見記:かんけんき)
西園寺実兼(さねかね)の長男西園寺公衡(きんひら)の日記。
母は源道成の娘の源顕子(あきこ)。