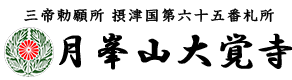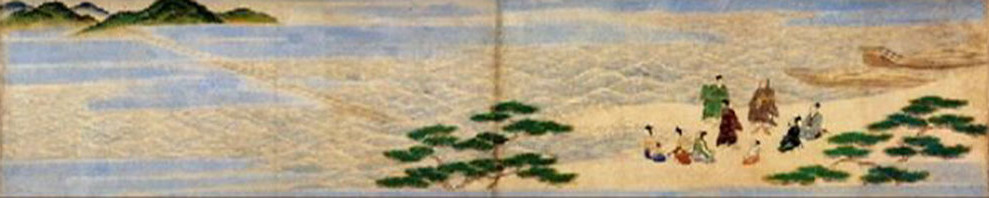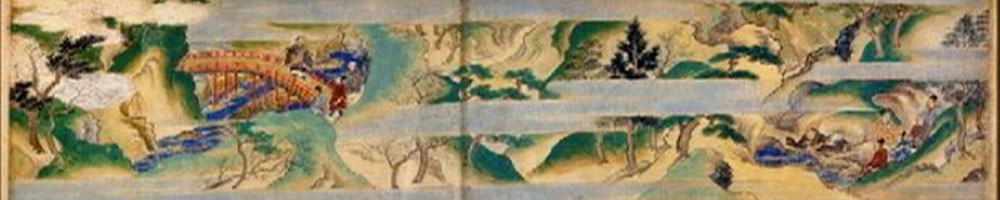鐘楼堂
黄鐘調の鐘 「天寿引摂鐘」
銘・「天寿引摂鐘」(てんじゅいんじょうのかね)
兼好法師の随筆「徒然草」第220段の中に「凡そ鐘の声は黄鐘調なるべし。これ無常の調子、祇園精舎の無常院の声(ね)なり。」とあります。
(黄鐘調:おうしきちょう/おうじきちょう:オーケストラのチューニング(音合わせ)でコンサートマスターの出すA(La)の音。)
「覚一本平家物語」を完成させた、覚一検校以下の琵琶法師たちの活動の拠点の一つであった大覚寺市庭に因み、「平家物語」の冒頭で語られる「祇園精舎の無常院の声」と言われる、黄鐘調の鐘を鋳り、「銘」を聖徳太子に因み「天寿引摂鐘」としました。
生者は鐘の音を聞くたびに、仏の加護を得て、天寿を全うし、死者には鐘の音は無間地獄の底まで響き、六道輪廻に沈淪すると雖も、聖徳太子のかの天寿国(浄土)に往生せしむ。
天寿国とは、聖徳太子が死後に行かれた国と伝えられる。極楽のことと言う。
引摂とは、必ず救いとる、迎えるの意。
開基1400年、開創730年記念事業・摂津尼崎大覚寺史料(一)が幸いにも、
皇太子殿下のご高覧を得る事と成りました、それを記念して鐘の銘に刻みました。